南部古代型染元 蛭子屋 (有)小野染彩所 は染色製品の製造を専門とする会社です。
〒020-0063 岩手県盛岡市材木町10-16
TEL 019-652-4116
TOPICS
 「南部古代型染元 蛭子屋 (有) 小野染彩所」
「南部古代型染元 蛭子屋 (有) 小野染彩所」 

- 【 https://katazome.jp 】 公式 website です
- 【English Guide 】【日本語ガイド 】 周辺地図・ACCESS
- 「南部古代型染」は、弊社のオリジナルブランドです。伝統的な技術をもとに、自由な発想で新製品を開発しております。古くて新しいライフスタイルをご提案いたします。
- <お知らせ>8月13日から8月16日まで臨時休業といたします
- 営業時間 10:00 ~16:00 (変動あり)
日曜定休日のほか 平日、祝日に臨時休業の場合がございます。
誠にお手数ではございますが
お確かめの上ご来店いただきますようお願い申し上げます。
<営業時間> 10:00 から 16:00 (変動あり) 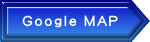
- 店内の様子
- 南部古代型染の三大行程
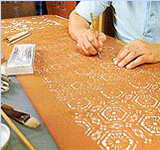
型彫は、基本となるデザインの型紙を切り抜いて模様を作ることから始まります。型彫りは、型染の最も重要な技法の一つで、 長い間の修練と根気を要します。型彫りには次の[突彫り] [錐彫り] [道具彫り] [引彫り]による四つの技法がそれぞれの内容によって用いられます。
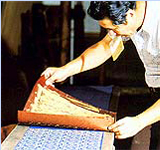
糊置は予め精錬(織糊、糸の油分を除く作業)した乾燥した生地に型紙をのせて上からヘラで糊を生地に印捺するものです。 その際用いる糊を防染糊と云います

藍染は材料に すくも藍、ふすま、木灰にて醗酵させたものを染浴とすることによる染色です。糊置きと藍染の合体により回数を重ねて好みの濃度に染めてゆきます。 使い込むほど藍独特の枯れた味わいを楽しむことができます。
絹、木綿、麻の染色に適しています。
代表的な柄
*向鶴*
南部公の紋章、向鶴を菱文に文様化したものである。この菱鶴の形状は、南部古代型独特のものです。
*千羽千鳥*
甲州南部郷の将、南部義光とともに三戸に渡った染師蛭子屋三右エ門は、海岸に群れ飛ぶ千鳥の美しさにみとれて、 その模様を型に彫ったものという。南部古代型の独特な模様です。
*萩*
南部古代型の中でも最古の模様と思われる。乱れ彫りの中に、線の流れの美しさがみられます。
NEWS新着情報
- 2023年9月20日
- "なび岩手" との相互リンク作成 https://naviiwate.com/
- 2023年 10月 13日
- English Guide Open

2024/06/27
弊社のすぐそば夕顔瀬橋より撮影
バナースペース
南部古代型染元 蛭子屋
(有)小野染彩所
Nanbukodaikatazomemoto Ebisuya Onosensaisyo
登録番号
T1400002000717
〒020-0063
岩手県盛岡市材木町10-16
TEL 019-652-4116
FAX 019-652-4105
E-mail
info@katazome.jp
公式HP
https://katazome.jp
<営業日> 日曜定休日のほか 平日、祝日に臨時休業
の場合がございます。
大変お手数ではございますが
お確かめの上ご来店いただきますようお願い申し上げます。
<営業時間> 10:00 から 16:00
(変動あり)
周辺地図・ACCESS
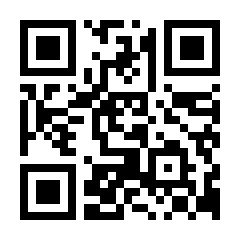
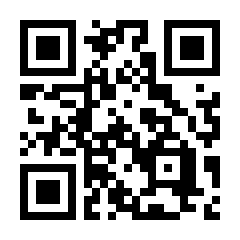
Offical Website